日テレ系のテレビドラマ『真犯人フラグ』がいよいよ最終回。
僕はミステリーものが好きなので、毎回ハラハラしながら、次回を楽しみにしてました。
このドラマも「考察」する方がネットで沢山いらっしゃるようですが、今回、敢えて僕はそれらを見ずに自分なりに推理したり考察しながら今日を迎えました。
というのも、僕はミステリーが好きなクセに、犯人やその動機を当てたりする推理力・考察力がなくて、大体最後には、
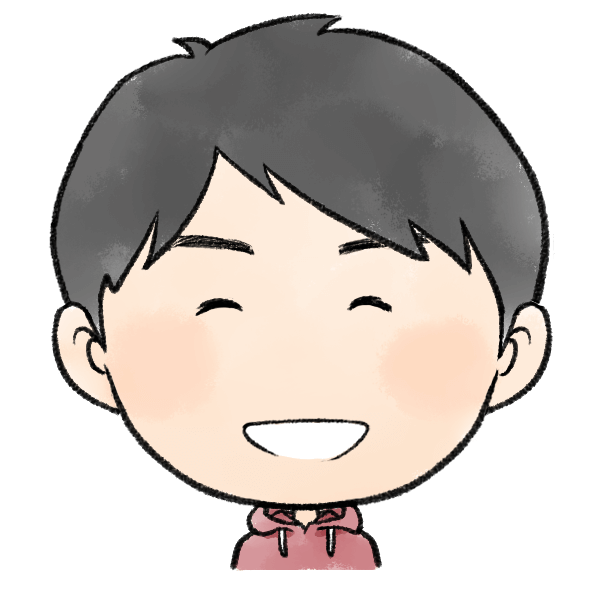
意外! あの人が犯人だったんだ!?
なるほどねー、そんな動機があったのね。
と、何となく楽しい気持ちになって、見終わったり読み終わる・・・のが当たり前でした。
でも、ここ数年、仕事の面で、上司や仕事相手から、
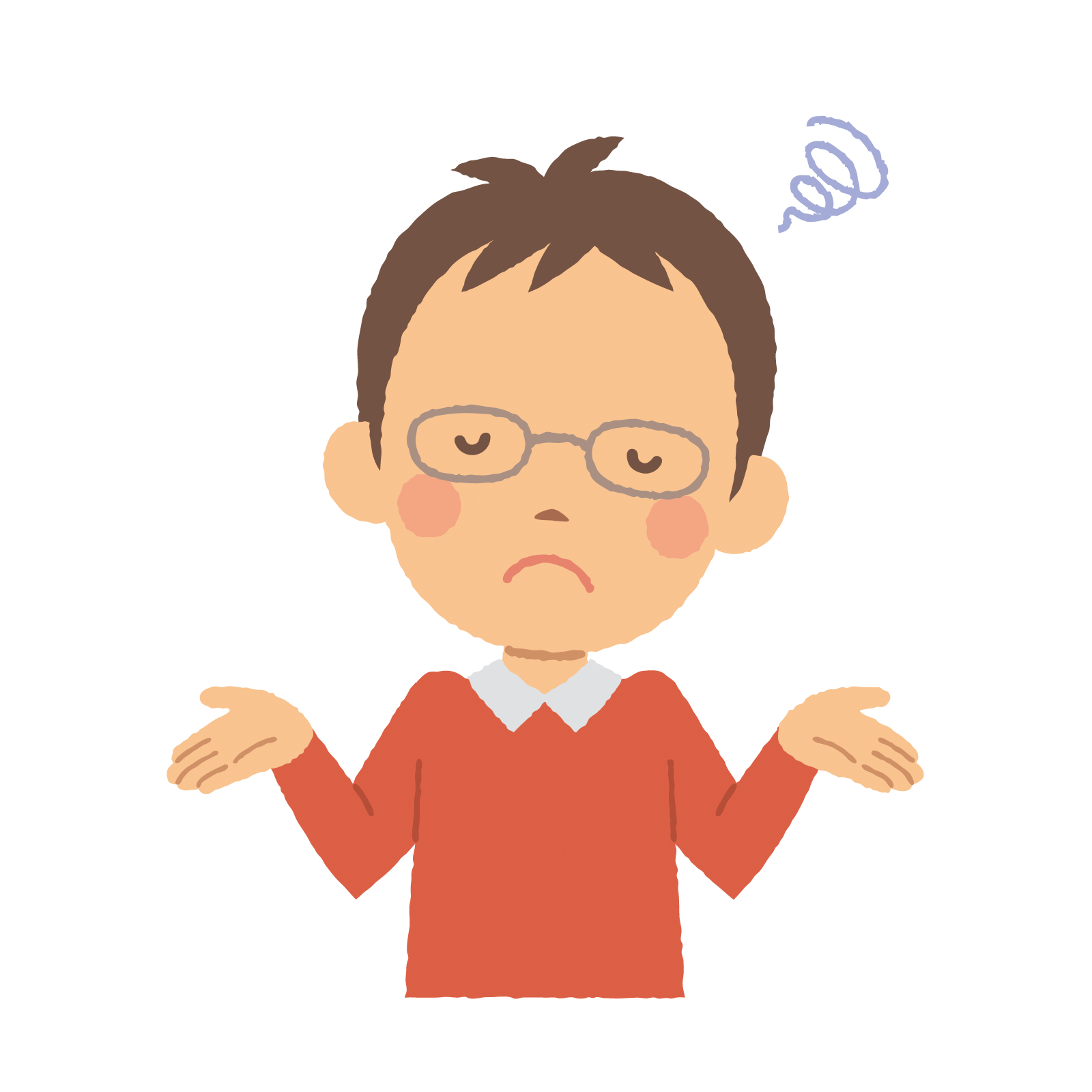
いや、そういうこと聞いてるんじゃなくて・・・
と言われることがたまにあって、
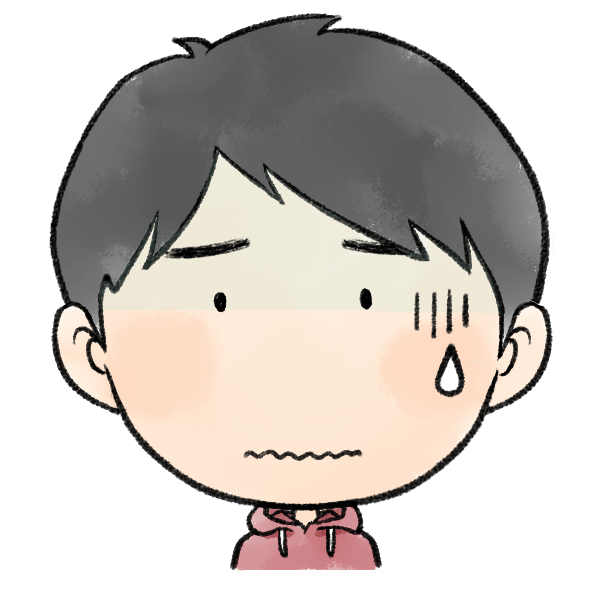
あれ?ちゃんと相手の立場を考えてたつもりだったけど、気持ちを理解できてなかったか・・・(汗)
ということが増え、他人の気持ちをもっと理解できるようになりたいと強く思うようになりました。
そんな中で、昨今のドラマなどの考察ブームとの共通点を感じ、「考察すること」について、今の自分が集めた情報や考察力を磨くために取り組んでいることをまとめてみます。
次のような方は、是非、最後までご覧ください。
- ドラマや漫画、アニメ等をもっと深く楽しみたいけど考察してる人のように気付けない
- 他の人の視点にうまく立てない
考察ブーム
冒頭に書いたテレビドラマ『真犯人フラグ』や、その前進となった『あなたの番です』(日テレ系)が空前の考察ブームを生んだことは、ネットのニュースにもなって社会現象と言われましたよね。
このように視聴者の考察が盛り上がったミステリー系連続ドラマも過去に沢山名作がありましたね。
僕が未だに印象に強く残っているのは、野沢尚(のざわひさし)さん作『眠れる森』(フジテレビ系)でしょうか。
アニメの世界では、昨年ついにラストを飾った『エヴァンゲリオン』の最後の劇場版が公開されると、YouTubeやSNS等で沢山の考察が発表されていました。
もっと遡ると、1990年代には、『磯野家の謎』という、サザエさん一家の様々な謎をまとめた本がブームになり、そこから「謎本ブーム」「考察本ブーム」なんてのも生まれました。
では、そもそも「考察」とは?
辞書ではこうあります。
[名](スル)物事を明らかにするために、よく調べて考えをめぐらすこと。「深い―を加える」「日本人の社会意識について―する」
引用元:goo辞書
「物語の考察」という観点で、もう少し言葉を加えるならば、
「結末・結果」の「原因」や「背景・前提」について、自分で考えたことを述べること。
ということになると思います。
結末・結果 = 事実・FACT
考察は、その「結果」となった原因や背景・前提となる条件などを考えて述べる事であって、「感想」とは異なります。
考察の方法
ここからは、実際の「考察の方法」について、僕なりに、いろんな方がやられていることを調べてみたことから要点をまとめてみます。
1.結末を考える
例)話のオチはどうなるか? 犯人・黒幕は誰か?
まだその物語が完結する前、途中段階であれば、一番の醍醐味はやはり、これでしょう。
2.その結果となった原因を考える
例)犯人の動機を考える あの人物はどうしてそんな行動を取ったのか?
僕的には、ここが非常に難しいです。
例えば、犯人探しものだと、
- キャストから考えて、この中の誰かでしょう?
- 一番犯人っぽくない人が犯人だよね?
といった考えから、何となく「勘」で犯人を当てられることはあります。
でも、これは考察でもなんでもなくて、たまたま、ラッキーパンチなだけで、当たってもあんまり嬉しくありません(苦笑)
3.その結果となった前提条件を考える
例)犯人にはどんな過去があるか?その中でどんなトラウマを持ち、どんな考え方になったか?
例)その登場人物は、過去にどんな教育を受け、何ができるようになったか?
例)時代背景、そのストーリーの世界観(常識、ルールなど)
2.の「原因」をさらに深掘りする作業です。
その人が「何故そういう考えを持ったのか」などの背景を勝手に想像したり、登場人物達の相関関係・人間関係や心の動き(心情や細やかな感情の機微)に思いを馳せるという思考です。
これ、こう書くのは簡単ですけど、実際なかなかできません。。。(滝汗)
4.他の人の考え、過去の類似策との比較
他に考察している人の考え・意見や、過去の類似作品との「差」を、自分自身の観点で考える。
これも、かるーく見たり読んでるだけでは当然できないので、やろうとするとかなりの気合いと時間が必要ですね。
5.作り手のメッセージ(隠れた意図)を考える
創作主(クリエイター)へのリスペクトを込めて、どんな意図で視聴者・読者に何を伝えたかったのか?
考察する人の、その作品に対する愛情の深さが現れる部分だと思います。
考察力を磨くには?
ここからは、まさに僕が今、自分を磨くためにチャレンジしようと励んでいることをまとめます。
まだまだ全然できません。本当に難しいです。でも、日々努力してます。
1.沢山の作品、沢山の意見・考え方に触れる
当たり前のことですが、
「人は「知っている事」しか知りません」
人は、経験したこと・学んだこと・考えたことがあることでしか物事を解釈できないんです。
「考えが思い浮かばない」のは、端的に言うと「まだ自分の中にないもの」だからです。
例えば、自分がまだ習っていない公式を使わなければ解けない問題は、どれだけ頭を使っても、基本的には知識の壁に阻まれて正解に辿り着けない、ということです。
だからこそ、 「人の感想や考察を沢山読む」。
これが今の自分には大切だと思ってます。
自分にない考えを他人から取り入れることで、今まで見えていなかったものが見えるようになって、考えが及ぶようになっていきます。
2.「理解不能な考え」を咀嚼する
他人の意見や考察に触れていて、自分にとってネガティブなものを見つけた場合、何故自分がそう感じたのか?という感情と向き合うことが大切です。
自分が全く理解できないような感性や生き方をしている人が、何故そういう言動をしているのか?
その思考の背景、前提を考えてみることで、自分の視野・視座を広げることができます。
3.意識レベルをあげる(ことを意識する)
たまに、アニメ等でその世界の「神様」的キャラが出てきたり、その作品の創作主がお遊び的に登場したりするものを見たことありませんか?
「神様の視点」、「世界の創造主(クリエイター)の視点」というのは、その世界の登場人物の視点より、高い視点であり、登場人物たちの考えや行動を探るうえで非常に重要な役割を果たします。
また、人は同じ”自分”であっても、時代や環境で価値観が変わっていきます。
子供の頃に見ていた作品を大人になってから見たら、全く感じ方が違ったりすることがありますよね。
登場人物たちの見ている視点・思考レベルをより高い位置から俯瞰してみたり、時間を過去や未来に動かしてみる事で、見えなかったものが見えてくるということがあります。
4.「答え」ではなく「問題」を探す意識
これも「あるある」ですが、番宣番組や解説本などで、
ストーリーの「謎」「伏線」まとめ
みたいなものがよくありますよね。
「これが謎だよ」と示されて、その答えを考えたくなるのが人情。
でも、明示された「謎」の答えを考えるだけでなく、「謎=問題・伏線がどこにあるのか?」を考えることで、考察をさらに深めることができます。
まとめ(所感)
冒頭に書きましたが、仕事上で相手から、「そういうことじゃなくて」と言われてしまった僕。
もしかしたら、
- 同じ人間なんだから、話せば最後は分かり合える
- 僕の言いたい事、わかってくれますよね?
そんな思い込みが深層心理で働いて、相手の気持ちを本当に理解しようとできていなかったんだと思います。
今の自分にないもの・考えを取り入れる努力をする
こういった努力の大切さに、「考察する」ということを考える中で、気付けました。
多様性の考え方にも通じる部分だと思います。
相手の意見・主張に「同感・同意」(=同じ気持ちになる)必要はないんです。
でも、「共感」(=相手の考え方を知る・理解する)ができるようになれば、見えなかった世界が広がって、人生がもっと楽しくなるんじゃないか?
今だからこそ、尚更、そんな風に感じて自分を磨いている今日この頃です。
少しでもみなさんのお役に立てたなら幸いです。

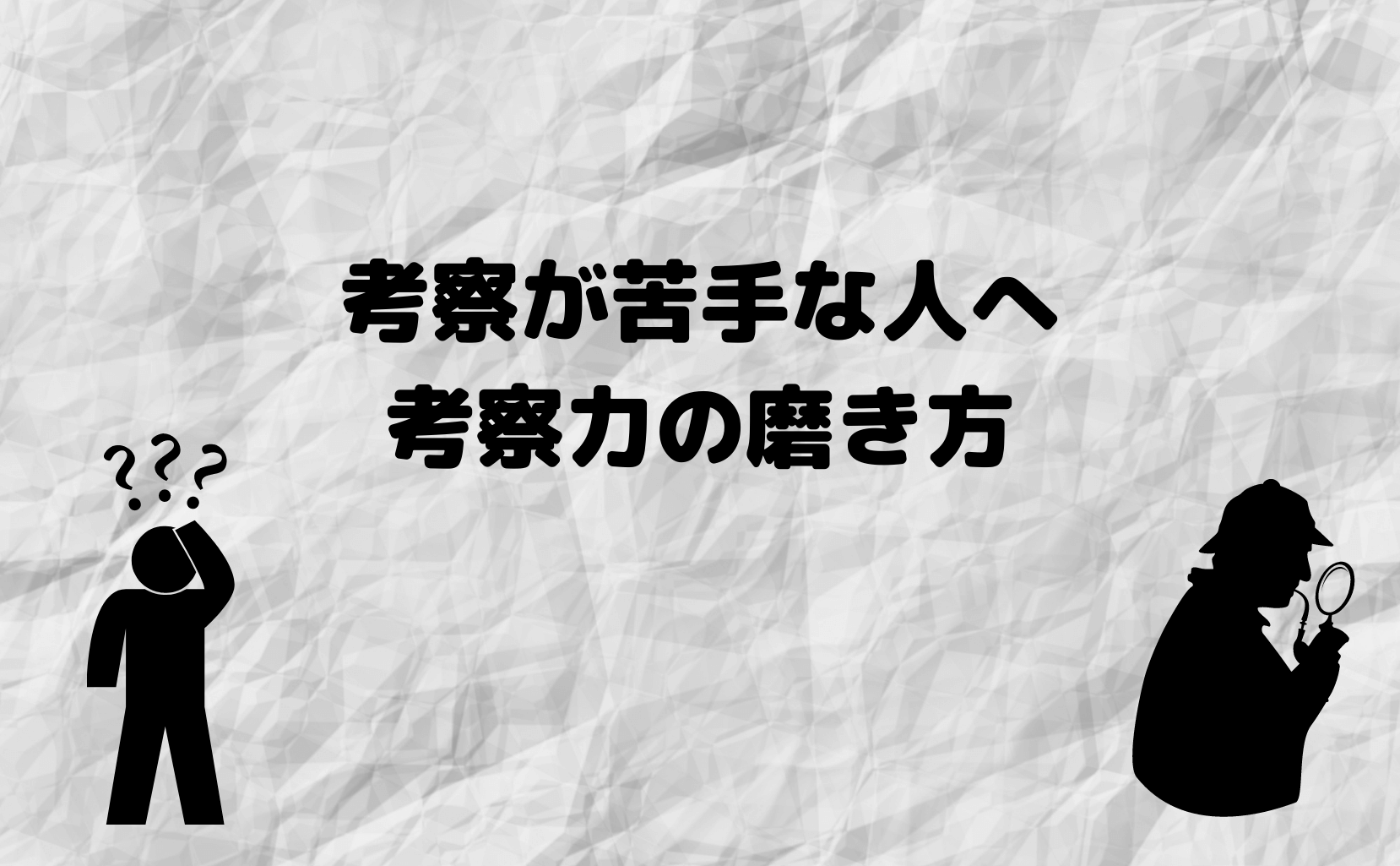
コメント