
どうも、かずです
日常生活を送る中で、人間関係で悩むこともありますよね。
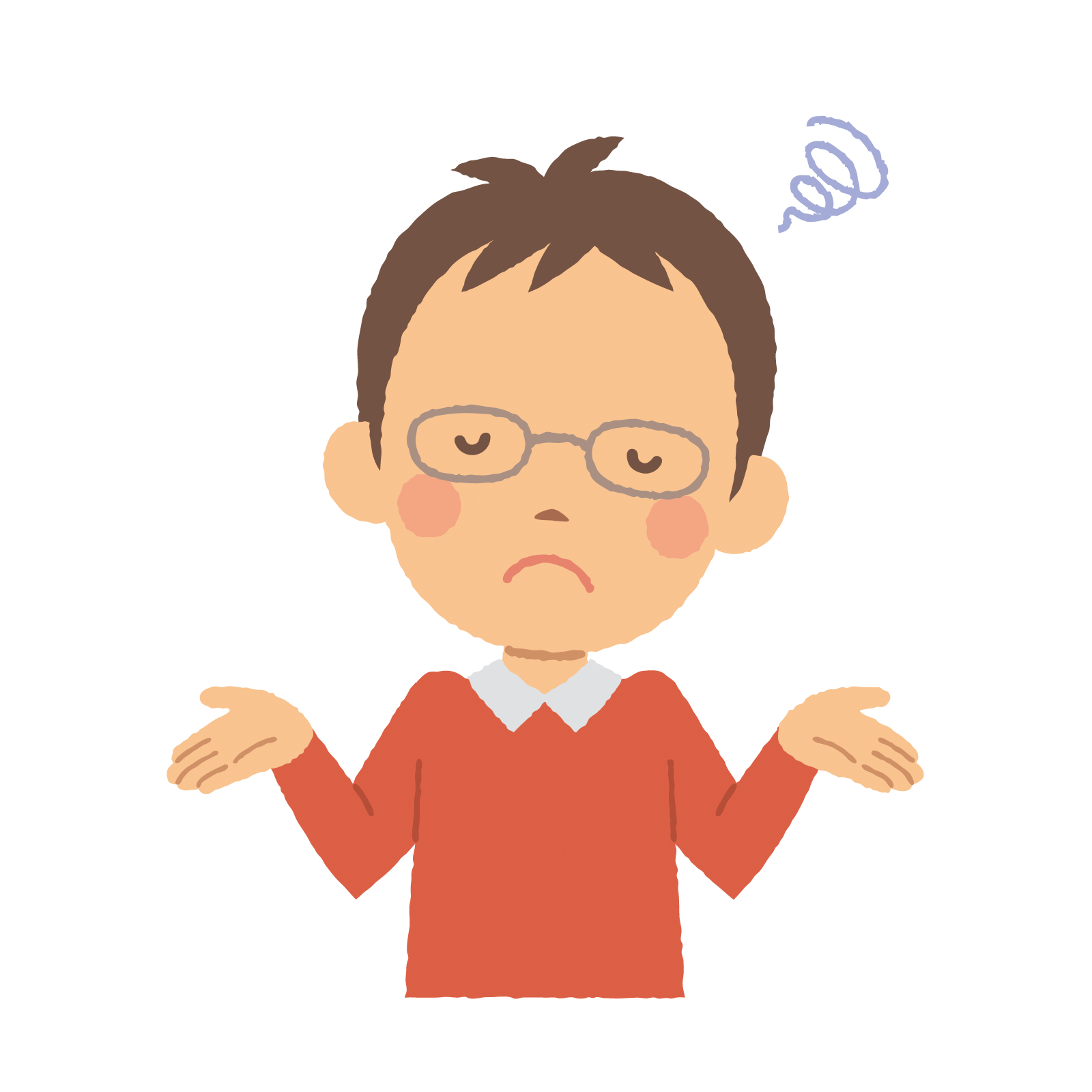
なんだかよくわからないけど、周りの人と話してて何かズレてる感じがしちゃうんだよな・・・
そんな感覚を感じる事もあります。
それが重なって「孤独感」につながってくることもあるかもしれません。
今回は、五木寛之さんの『孤独の力』というエッセイ本を読んでみて僕が感じたことをまとめてみます。
ご興味のある方は是非最後までご覧ください。
五木寛之さんのプロフィール
まず、五木寛之さんのプロフィールから。
1932年9月30日生まれ(2022年4月2日現在、89歳)
小説家、随筆家、作詞家
生後間もなく父親の勤務で朝鮮半島に渡り少年期を過ごす。
1947年 15歳の頃、朝鮮から福岡県に引揚げ。
作詞家を経て、1966年 小説『さらばモスクワ愚連隊』でデビュー。
1967年 『蒼ざめた馬を見よ』で直木賞受賞。反体制的な主人公の放浪的な生き方や現代に生きる青年のニヒリズムを描いて、若者を中心に幅広い層にブームを巻き起こした。
その後も『青春の門』をはじめベストセラーを多数発表。
近年は人生論的なエッセイや、仏教・浄土思想に関心を寄せた著作が多い。
引用元:Wikipedia
今回ご紹介する『孤独の力』の中でも、幼少期を過ごされた朝鮮半島でのお話が出てきます。
幼少期の体験やそこで感じた感情が、今の五木先生の哲学に大きな影響を与えているんだとわかります。
エッセイ『孤独の力』を読んで
五木寛之さんご自身の人生経験をもとに、「孤独」というものについて、様々な宗教観や現代の人々の思考などと共に掘り下げていくエッセイです。
いつの間にか、日本人の多くの人には、
「孤独は良くない」「孤独でありたくない」
という考え方が広く伝搬している。
しかし、本当に「孤独」はただ寂しくつらいだけのものだろうか?
そんなことがテーマです。
人間には、様々な感情があり、
「安定」「つながり」を求めたい気持ちと
「自由でありたい」「自分の個性・尊厳を大事にしたい」という気持ち
それぞれが内在しており、それがゆえに「葛藤」が起こる。
この本では、徘徊老人の感情を例に挙げ、施設で過ごす老人の中には、
潜在的には心の中で
「独りになりたい」「動き回りたい」「群れを離れたい」
という願望を内側に抱えているのではないか?
それは、人間の正直な本能的な反応ではないか?
という主張がされています。
一方、そのように集団から離れて放浪するような存在に対し、集団の中にいる人たちは「不安」や「恐れ」の眼差しを向ける。
それは、自分達の生き方(定住・定着)が否定されそうな気がするからだ、と。
確かに、僕にもここで書かれているそれぞれの感情がすべてあります。
立場や状況、時期によって、どの感情が出てくるのか、強いのか、が変わってくるということだと思います。
五木さんは、前述のとおり、生後すぐに朝鮮半島に渡り、第二次大戦中、そこで幼少期を過ごされます。
言葉も文化も違う学校生活の中で、なかなか集団に打ち解けることができず、孤独な日々を送る中で感じたこと、学んだことをじっくりと書き留められています。
そして、まもなく90歳を迎える五木さんは、定年退職後のいわゆる「余生」について、こう語っています。
「余生」は”人生の余った時間”ではない。
人間の孤独というものを見つめながら生きていかねばならない大事な時期。
その時期になる前に、その時期のことを念頭に置きながら、自分で何をやるべきか、考えながら生きていかなければならない。
引用元:『孤独の力』より
「人は、一人では生きていけない」
とよく言われます。確かにそうだと思います。家族や友達、コミュニティがあることで救われていることは間違いありません。
でも、結局は、「他人は他人」であり、最後は「自分自身」で選択し、動かなければ生きていけないんですよね。
そこで、この本における五木さんの最大の主張に繋がります。
人々の中に生き、活動を続けながら、自分が孤独であるということを自分なりにちゃんと確認し、その孤独に耐える力を大事にしていくことが、今の私達にとって一番大切。
引用元:『孤独の力』より
僕もずっとサラリーマン生活を送ってきましたが、その中で慢心や甘えが育ってしまっていることにハッと気付かされました。
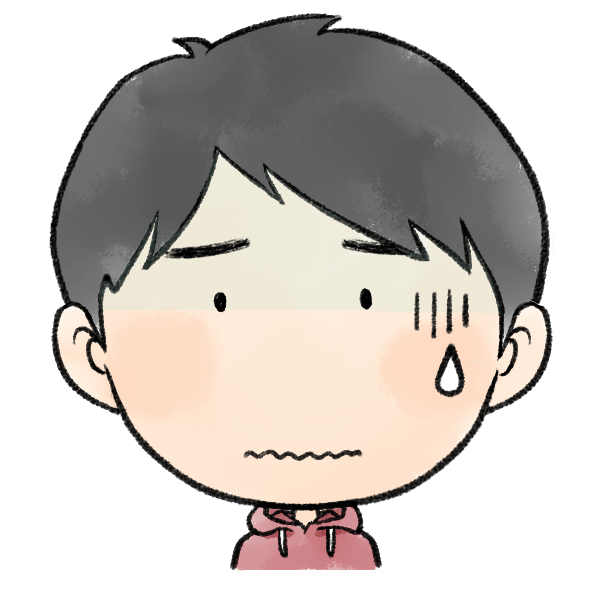
最悪、うまくいかなくても誰かが助けてくれるだろう・・・
そんな気持ちが、常に心のどこかにありました。
でも、実際に自分に向けられて剛速球でボールが飛んできたとして、逃げもできず、誰も守ってくれない状況になったら、今の自分は無抵抗でそのボールを食らうしか選択肢がないかもしれない。
そんな考えにいたり、急に怖くなってしまいました。
孤独を恐れたり、孤独に耐えられないような弱い心では、生きてゆくのがつらくなる。
そんな五木さんの言葉にも、心が揺さぶられました。
また、この本では仏教やキリスト教の宗教観についても触れられています。
僕は正直、ほとんど宗教に関しては無頓着で、最低限の知識・理解しかありませんでしたが、この本でその考え方について理解を深めることができました。
仏教の祖・ブッタが一貫して唱えていたこと。
世の中は無常に移りゆくのだから、執着のないようにいつも気を付け、独りで確信をもって歩め
僕はこれを、
目の前の一つ一つの事象に一喜一憂しすぎるのではなく、長く広い視野を持ち、しなやかな思考を持つことの大切さ
を言っていると考えました。
また、キリスト教のイエス・キリストの孤独感の根底には、
「人間というものは裏切るもの」「人間というものは罪あるもの」
という考えがあると言います。
それが悪いということではなくて、そういう前提で生き、
自分を裏切る者、自分に対抗してくる者をも認め、ゆるしなさい。
つまり「汝の敵を愛せよ」という教えなんだと思います。
これってすごく難しいことですよね。
頭では「言いたいことはわかる」。
でも、実際にそれができるか?と言うと、いざそういう場面に直面したら、やっぱり抵抗するか逃げるか、従属するか・・・そんな対応をしてしまいそうです。
僕自身、かなりその傾向が強いと気付いたのですが、人間は、
「二者択一」「白か黒か」「正解か間違いか」
という考え方を瞬間的に持ちやすい性質があるんだと思います。
「どっちの味方なんだ?」
とか問い詰めてくる人もいますよね^^;
また、それに対して、少し冷静に考えたとして、
- 相手を否定する・反論して自分の意見を主張する
- 両社の意見を融合し、妥協策を検討する
のいずれかの打ち手に落ち着かせることが多いなと感じます。
でも、別の選択も取れるはずなんです。
- それぞれの異なった考え・意見を混ぜることもなく、同時に認め、共存させる。
- 人によって求める価値観・優先度が違うという前提に立ち、すべての意見を残す
という選択。これこそ多様性ですよね。
五木さんは、この本で「孤独」と「孤立」の違い、ということも語っています。
「孤立」は、他者を寄せ付けない、排除するという感覚。
「孤独」は、来る人拒まずだが、独りでいることを悲しいともつらいとも思わない。「独立自尊」の考え方。
自分もそんな考えの域に達することができれば、強くなれるなと感じます。
まとめ(感想)
この本を読む前、僕は
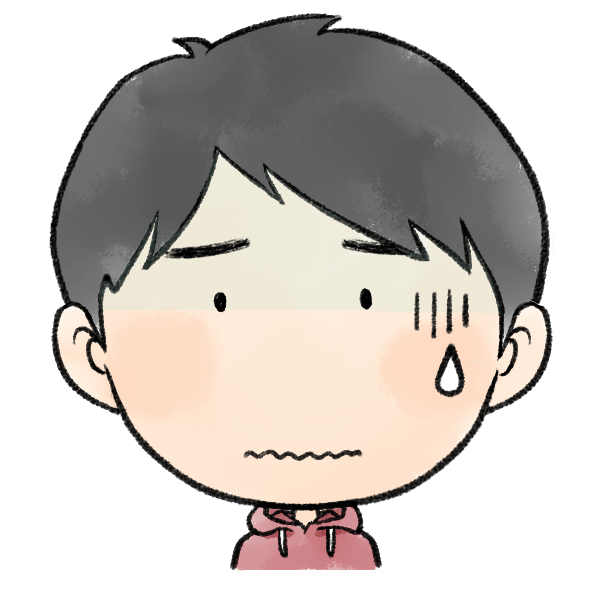
どうやったら「孤独」を回避できるかな?
という考え方をしていました。
ある意味、「孤立」と「孤独」を混同していたんですね。
「独立自尊」
いい言葉を知りました。
他者を否定したり、拒絶するのではなく、誰のどんな考え・感情も受け入れた上で、「自分の感情・考え」をしっかりと尊重できること。
「独りでいる」というフィジカル的・物理的なことというよりも、精神・心理面で、「自分の心や感情」を周りに埋もれさせないこと、蓋をしないこと。
それが、「孤独の力」なのかな、と僕はこの本を読み解きました。
日常に忙しい中にいると、ついつい自分の心や感情を見失ったり、置いてけぼりにしてしまいます。
そして、それが長期間続いていくと、自分の中の「心」が、「今、表に出ている自分」を信じてくれなくなります。
それは、自分も周りの人も不幸にする状態だと思います。
僕は、日々、自分の感情、特にマイナスな感情を感じ取ったら、しっかり時間を取って、その感情と向き合い、ちゃんと受け止める、ということを日課に加えました。
こうして毎日、歯を磨くように心もクリーニングして、「自分」というものを強く持てるようになっていきたい。
そう考えさせてくれた、素敵な本です。
もしこれを読んでご興味を持ってくださった方は、是非読んでみていただければ嬉しいです。

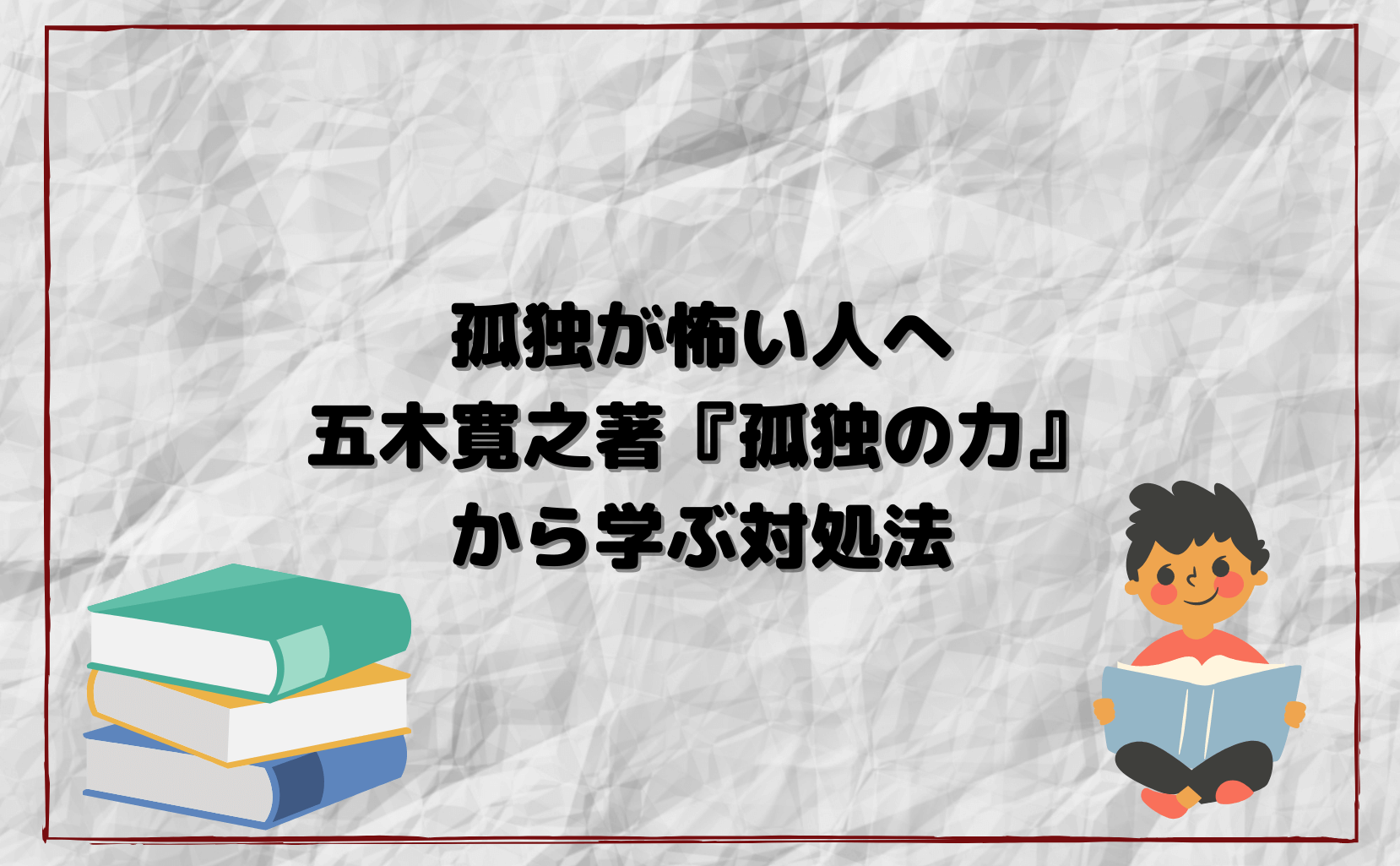
コメント